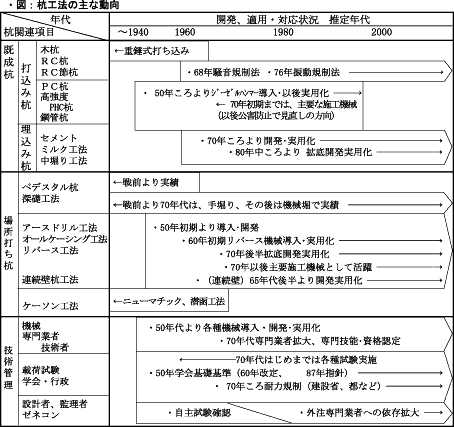戦後の建築工事は、1945(昭和20)年以後一時低迷があったが、その後の社会的な変化に伴い1950年ころから活気を呈し始め、1960(35)年にかけて施工方法も戦前のやり方から少しづつ変化していった。さらに1965(40)年頃からの好景気による各種の技術開発により工事の施工計画や施工方法も大きく変換し、これらの技術がその後も改善されながら、現在も継続されてきている。
これら多くの各種技術開発に対し、これらがその後も実際の建物に活用されたかについては、結果的には「1.汎用的に」に活用されたものと「2.特殊対応」として活用されたもの、更には「3.試行レベル」で眠ったものとに区分できる。技術の活用には、経済性や工期への対応が従来の業界の体質からくる問題と大きく関わりがある。
上記2,3項についてはともかく、1項の汎用性に関わる技術については開発は出来てもそれなりの適用努力が必要である。
すなわち、一般的に汎用化されるためには、現状の問題点・やり方、契約取決め条件との調整、改善・試行、効果の把握、そしてこの繰り返し作業を、誰が中心的に行うか更には関係者が新技術にどの程度積極的に対応していくかを認識し水平展開していく努力が必要である。3項は結果的にこれらの条件がそろわず、消えていった技術といえる。
しかし、1985(60)年から平成に入って建物のローコスト化や品質確保要求の中で、これら新技術の見直しが新規の開発と共に進められてきたが、現在の顧客指向やIT化指向の拡大の中で今後の設計・施工のあり方も変換の時期にきていると考える。
以下上記の特に1,2項に関連した戦後からの技術事例について、下記の視点より項目別に述べてみたい。
1)材料、工法、専門業者、設計者、ゼネコン 2)各工法の問題と反省
3)技術の伝承
■杭工法の変化:打ち込み杭から場所打ち杭へ
戦前から、戦後しばらくにかけて杭工法については木杭、既成杭やペデスタル杭など打ち込み工法が全盛であった。 1955(30)年代中頃より建物の大型化、欧米の杭機械の開発等によりアースドリルやオールケーシング(ベノト)等の大口径場所打機械が導入され始めた。
その後1965(40)年代に入り工事量の増大、打ち込みによる騒音・振動問題など社会公害の発生への影響から打ち込み工法は急激に減少し、大口径杭なしでは対応できない状況になってきた。
当初の大口径杭は、せいぜい直径が1.0m前後であったものが、50年代に入り2.0~3.0m、更には先端または杭頭部分の拡大工法が開発され、建築センター認定工法としてオーソライズされてきた。また施工技術者についても1975(50)年代後半には、専門の資格者認定による方向に動き始めた。一方従来の打ち込み用の既成杭についても、専用の機械開発による埋め込み杭への採用へと変化し、打ち込み杭の採用は、公害などの影響の少ない地域の施工に限られてきた。
現状は、上記大口径の場所打杭と埋め込み杭が活用の主流となっているが、杭耐力の確保の面から見ると、杭は出来上がれば土の中で目に見えないものであり、施工中の品質管理が重要なポイントとなる。
打ち込み杭については、従来から貫入試験、算定方法で比較的容易に耐力を判定できる状況にあるが、場所打ち杭や埋め込み杭については、施工直後では耐力の判定が困難であり、施工中の手順、チェックを踏まないと問題が多い。杭耐力の確保については、当初は機械操作者や現場管理者も今から見れば未熟な点はあったが、慎重な取り組みで対応 していたと考えられる。
1965(40)年代後半からは工事量の増大に伴い、専門業者への依存度合いが急激に増大し(杭工事に限らず)、先の専門技術者認定対応の例があるが、現在を含めて元請けの管理が希薄になっているのが現状である。
幸い、現状の杭耐力の認定は、種々の条件で低く押さえられており、問題の発生は少ないようであるが、スライム処理の不徹底、コンクリート充填性の不良、鉄筋配筋・かぶりの不良などが問題とされていたが、 近年既存建物の解体などでこれらの問題が露見している例もある。
1975(50)年代の超高層ビル時代以後建物は益々大規模になり、一本あたりの杭耐力も増加しており、工期、経済性を踏まえた品質確保の点からは、目で確認できない部分であり、今後の施工管理でもっとも注意すべき事項と考える。