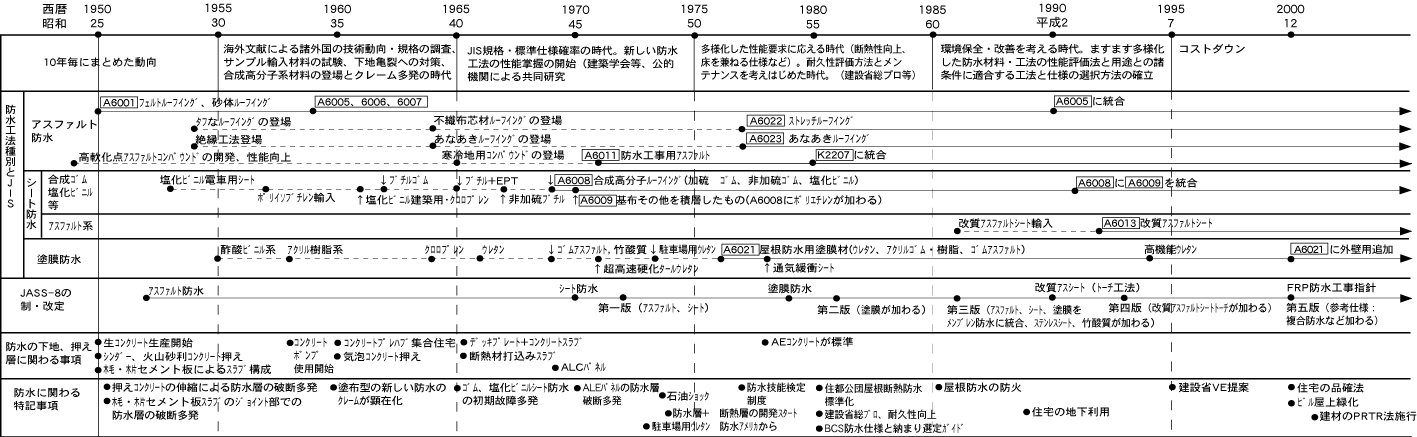新入社員にとって最初の防水との出会いは、登場して2〜3年目のアクリル樹脂エマルシヨン塗布防水の施工中のクレームであった。この防水材を勾配屋根部分に施工、硬化途中の降雨で流されてドレン周りに大型シャボン玉状の深さ20〜30cmの大きな樹脂入り水溜りが出来、それがオーバーフローして壁に白い汚れた皮膜を作っていた。その現場所長は、“化学防水”には困ったもんだ、技研の人で誰か防水に取り組んでもらわんと、大変なことになるよとの要望があった。程なくして気がついた時には、先輩格の酢酸ビニル系の同様な材料とともに、市場から消えていた。1905年以来、トップの座をキープし続けてきたアスファルト防水材メーカーから見れば、黒船沈没?の感じであったことと思う。
新材料・新工法登場の動機には、品質向上、工期短縮、コストダウン、最近では環境への配慮などがある。前述の塗布防水は、メーカー主導の“売らんかな”での参入、つまり需要者側の要求に基づかないがゆえの失敗だった。しかし、1960年から約10年の間に新たに市場に出てきたものの多くは、屋根スラブ構法の変革を背景として開発されたものだった。私がこの世界に首を突っ込んだ時には、鉄骨造でスパンの大きい工場建屋の屋根スラブの多くは、細い径の鉄網で補強された木質成形パネルで構成されていて、しかもパネルの母屋上ジョイントで防水層が破断、漏水に悩まされていた。アスファルト防水メーカーでは、よく伸びてしかも丈夫なルーフィングの開発を進めていた。東京・晴海埠頭に1959年竣工の、鉄骨シェル状見本市用施設の屋根防水層を後年改修した際に、合成繊維織布を芯材とした強靭なルーフィングが採用されていたことを確認している。
もうひとつ、シンダー(石炭殻)コンクリート押さえ層が膨張してパラペットを押し出し、その際に入隅部の防水層破断のクレームが多発していた。当時の設計と施工の標準では、パラペットはシングル配筋だったこと、パラペットのコンクリートはスラブの天端とゾロで打ち継がれていたこと、押さえコンクリートの伸縮目地間隔は、約9m(昭和27年版、建築工事共通仕様書、建設省営繕局)と現在の3倍近くもあったことなど悪条件が重なっていた。しかし、火力発電所や蒸気機関車からの廃棄物である石炭殻を押さえコンクリートの骨材として用い、伸縮の大きい寸法不安定なコンクリートであったことに根本的な原因があった。その後、現場打ち気泡コンクリートが開発されて被害はさらに拡大、押さえのある防水層受難の時代がしばらく続いた。前述の“化学防水”は死語になったが、中味が変わったにも拘らず、今でも「シンダー」の名称が残っていることに対しては、嫌悪感を抱いている。
同じころ、塩化ビニルのシート防水の開発が進められている。塩化ビニルシートは、昭和26年に横浜・桜木町駅構内で発生した架線切断による電車の屋根火災事故対策として、従来のアスファルト系シートから塩化ビニル系に置き換える過程を経験している。その後1962年頃に、合成ゴム系シートが登場した。1960年代前半はシート防水揃い踏みの時期で、いずれにしても”良く伸びること“という要求に対応した製品であった。 1960年代後半にはALCパネルが国産化され、前述の木質成形板を置き換えてゆくが、パネル相互のジョイント部分の変位に対する耐久性確保は一段と強く要求されるようになる。合成ゴム系シートの一部に、空気中のオゾンにより微細な亀裂が発生、漏水が多発した。配合上の改善策はとられたが、今度はシート相互の接着耐久性に難点が生ずる等、産みの悩みがしばらくは続いた。防水層が破断した、パネル類で構成されたスラブの母屋上ジョイントムーブメントを実測したところ、木質成形板(長さ1.5m)では日間最大1.0mm、ALCパネル(長さ2.0m)では、日間最大2.74mmが記録され、防水層の性能評価試験方法作成時に、一つの資料として提供できた。
1955〜65年にかけて大きなクレームを経験した液体状の材料を現場で塗布する塗膜防水は、主剤と硬化剤を混練、反応硬化させるウレタン防水が1966年に登場する。当初は物性、施工性ともに完成度はいまひとつであった。しかし1971年に登場したタールウレタンをハイテクな機械を使って瞬時に硬化させる工法は、防水工事を大きく変革させるものとして注目された。
丁度そのころ、デッキプレートを型枠代わりとしてスラブコンクリートを打設する構法が普及し始めた。コンクリートの水分はデッキプレートと防水層に挟み込まれ、太陽熱で水蒸気になり防水層の膨れが多発した。既存の工法はいずれも下地に部分的に接着・固定する手法で対処、ウレタン防水は誕生時が丁度この時だったので、しばらくは苦難の道を歩んだが、1978年に通気緩衝シートが開発され、膨れ防止工法が全部そろったことになった。
1973年、防水層は防水だけしていればよいのだという考えを大きく改めさせる工法が登場した。それはアメリカからの駐車場という床機能と、防水機能をひとつの材料で賄ってしまおうという工法である。ウレタン防水にノンスリップの骨材をつけたものであるが、その後国産品も登場、さらにポリエステルとの積層工法なども加わった。複合防水に先鞭をつけた多機能化の幕開けだった。
その次の大きな問題は、1973年〜74年の第一次石油ショックで、北海道など寒冷地では早くから結露防止のためにコンクリートの内側に断熱層を設ける、いわゆる内断熱が普及していたが、快適な環境空間作り、建物躯体の長寿命化などを考えると、建物の外側に断熱層を設けるのは自明の理であり、日本住宅公団では1975年から数年がかりの研究を経て、1980年からこれを標準化した。コンクリートスラブ直上に防水層を、その上に断熱層を、そのまた上にコンクリートを保護層としておくもので、現在に続いている。欧米では当たり前であった外断熱工法を率先して採用した功は大きい。このように断熱材の上にコンクリートが直接載る場合は断熱材の含水が問題だったが、押し出し成形発泡ポリスチレンで対応できることが確認された。同時に、防水層が断熱層の上に来る露出防水仕様の検討も各機関でなされた。断熱層上の防水層の温度は一段と高くなるので、防水材の劣化は進むことになる。耐久性は低下するがその状況を目視などでフォローできる露出型の防水がよいか、劣化状況のフォローは出来ないがさらに一層の長寿命を期待できるほうがよいか(断熱層の有無とは別にして)、大きく意見が分かれるところである。
「環境」は目下の重要な課題である。前述の断熱防水 も快適な空間作り、躯体の長寿命化等、広義の環境面で貢献している。また、防水層構成材料が製造時から廃棄処分時まで、空気、水や土を汚さず、人体に悪影響が無く、またリサイクルやリユース性に優れることなども求められる。施工時の環境改善も重要である。しかもコストダウンという社会からの強い要請にも対応しなければならない状況におかれている。“幸か不幸か”多年にわたり長期保証を求められてきたこの業界にとって、これに応える事は難しいことではないものと確信している。
*1 東京工業大学名誉教授、小池迪夫氏調査による